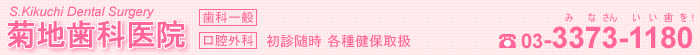上の親知らずが下に伸びてきて、下の歯ぐき、及び下の親知らず周辺の歯ぐきを傷つける場合があります。
また磨きづらいことに加え、食べカスが停滞しやすい為、特に上の親知らずは、頬の側に大きなムシ歯をつくってしまいます。
ムシ歯で溶けてしまった歯の表面が、欠けたり、尖ったりして、頬の肉を傷つけてしまう場合もあります。
顔を出している程度にかかわらず、親知らずが周囲の組織に悪い影響を与えることがあります。傾いたり、真横に向いた親知らずにより、第二大臼歯が影響を受けます。常に押す力が加わることにより、第二大臼歯の根が吸収されてしまうこともあります。
また、侵入した細菌によって、第二大臼歯の根の部分がムシ歯に侵されてしまうこともあります。この場合、当の親知らずは、硬いエナメル質の部分が程度の軽いムシ歯で済んでいるにもかかわらず、そのとばっちりを受けた第二大臼歯の柔らかい象牙質(セメント質)の部分が、ひどいムシ歯となってしまうケースもあります。
当然、歯肉に内部で起こっている出来事ですので、日々のブラッシングを完璧に行っていても、鏡を覗いていても 自分で気付くことができません。また歯肉の内部の根に発生したムシ歯を治すことも、ほぼ不可能です。
親知らずを抜いてしまうのは仕方がありませんが、歯の頭の部分を完璧に磨いていたはずの第二大臼歯を抜くハメになってしまう、大変不幸なケース(写真0019&0017&0021)と言えましょう。
親知らずがムシ歯にならずに、手前の歯の根がムシ歯になっているのはなぜでしょうか。
歯の頭の部分はエナメル質で出来ています。これはダイヤモンドに匹敵する硬さです。一方、根の部分は象牙質(正確にはセメント質)になっていて、硬さはエナメル質の10分の1程度で
す。 その結果、大切な第二大臼歯の後ろ側が虫歯になってしまうことが多くみられます。
|